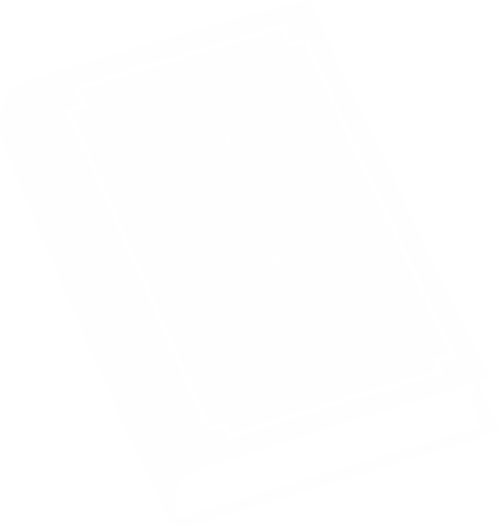イヴ。寒さで目の醒めた、夜。
道に迷った。
わざと迷ったのかもしれない。
「迷った、迷った」と思うことでこれからすべきことを、どこか知らないところに置いてこようとしたのかもしれない。
大阪から和歌山へ抜けて、このまま海沿いを行けるところまで走ろうとしていた僕の車は、一瞬で唐突な憂鬱に襲われて京都へ進路を戻した。
今まで途中で引返したことなんてなかったのに。
引き返すことのできる道を選んだことなんてなかったのに。
夜半過ぎに京都に着く。
何となく家のドアを開けるのが嫌で、停めた車の中で大黒屋で買った生のキャベツを噛む。
生のキャベツの味がする。
スーパーで買った生のキャベツの緑はいかにも真っ黒な車内に映え、助手席に座らせて眺めてみたりする。キャベツとドライブもイヴにしては悪くない。
楽しい時間が先にあるとその分だけ憂鬱が濃い。
生のキャベツの味みたいに濃い。
道に迷ったのは帰る意志があったからだ。
2年前、日本中の美術館をまわろうと思い立って車中泊で際限のないドライブを続けた。
その時はどんなに知らない道を走っていても前のベクトルに向って走るような昂揚があったし、「迷った」と自覚することもなかった。たとえ目的地に最短経路で到着することはできなくても、その分だけ違うものが見れて幸せだと思った。
ずいぶん前向きな話だ。
今は後ろ向きなのか、と聞かれたら案外そうでもない。
ただ、人といる時とひとりでいる時の差が大きくなっただけにすぎない。
目覚めることのない夢を見る。