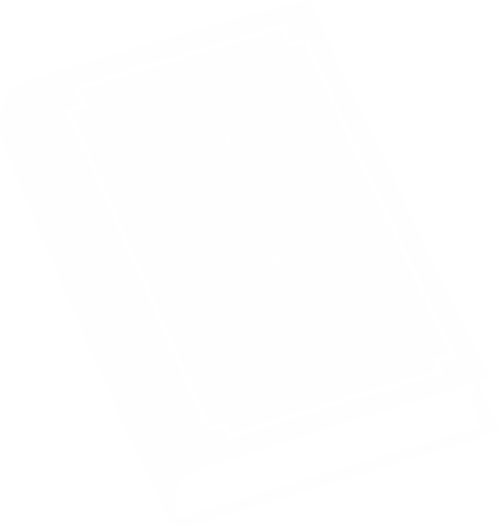黄昏。
砂のことを考えていた。
土より砂が好きだった。身近だったから。
畑を耕す記憶。干上がった水田で稲を刈る記憶。湿ったすえた匂い。熱い。
暖かいものが気持悪かった。肌のぬくもりは嫌いだった。
離れない子供。離れない自分をわかっていてわざと離れない。
「離れたくない」のではなく、「離れてはいけない」という思いをもった乾いた子供。
砂。
僕は砂だ。土に寄り添った人間を遠ざける。
太陽の熱を生きるため必死に明日へと懐へ繋ぎ止める、土。
まわりのものと相互に関係を維持しながら、肥大する。土。
べっとりと手に貼り付いた土を、僕は何度忌み嫌ったことだろう。
はかないと知っているものを、「はかない」と口に出しても冗談にしかならない。
何かを繋ぎ止めようとする努力は、何かを拒絶しようとする努力と等価でしかない。
風が吹けば、砂は消える。
消えるけれど、砂自体が消えてしまったわけではない。
ただまたいづれ空気や時間の流れが、
新しい一粒ひと粒を集めるそのときまで
まるで群れ寄り添って互いを破綻させることを恐れるように
いなくなる。
いない。
僕はどこにもいない。