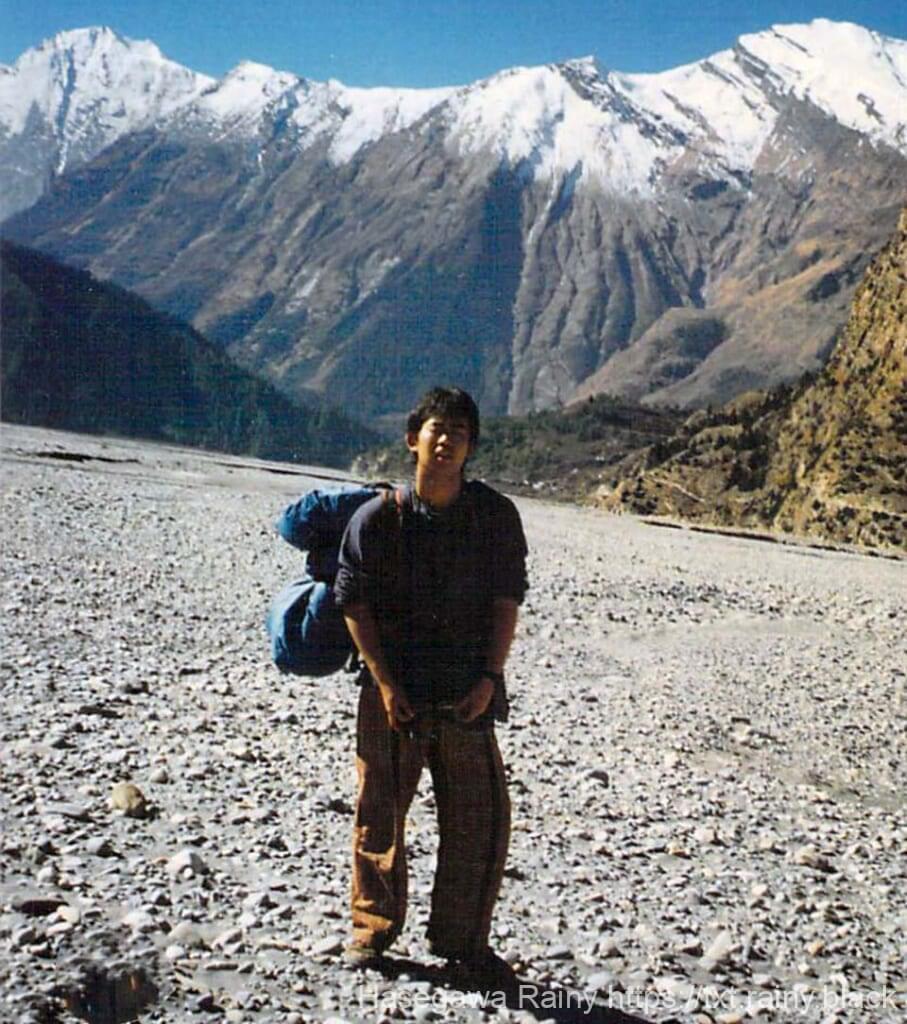夢を見た。
夢のなかで記憶がハウリングし錯綜する。
死んでしまった人々が整然と並び、消えてしまった人々がひとり芝居をする。
僕は小さな芝居小屋にたったひとりきりの客として、
僕の中で死んでしまった人間たちの独白を聞く。
その言葉はうまく聞き取れない。
ウエムラくんは病弱で線の細い、色の白い子供だった。
小学生の間、よく遊んだ。
暗く憂鬱で学校嫌いだった僕は、同じようにもの静かでおとなしい彼と草や花をつんで遊んだ。
うちの田畑を歩いては二人で虫を捕まえたりレンゲの蜜をなめたりして一日を過ごした。
そんなこと、もうすっかり忘れていた。
僕にとって小学校は思い出さないように鍵をかけた記憶だ。
ウエムラくんはおとなになれなかった。
肺炎をこじらせてあっけなく死んでしまった。
中学にあがってすぐのことだ。
それを聞いて僕は全く哀しまなかった。涙も出なかった。
あのすすきの生えた土手を二人で歩いた時にもう諦めていたのかもしれない。
お互いが「どこか壊れている」ことをちゃんとわかっていたのかもしれない。
彼の体はこころとともに崩れおち、僕は処世を覚えて偶然生き残った。
ただそれだけのこと。
彼の死を知った日、僕はバスケットボール部に入部する。
夢が引き金となって忘れていたことを思い出す。
思い出したくなかった事柄の方が多い。
けれど時にふっと思い出すこれら消え去った人々の記憶は、
彼らが消え去る度に空けていった僕の中の真っ暗な穴を、
今さら彼ら自身が詫びるかのように甦る。
僕は夢の中で彼彼女らのよく聞こえない独り芝居を観ながら、
消えてしまった彼彼女らにはもう僕の中にさえ戻る場所がないのかもしれない、と考える。
僕は本当に大事にしていた人のことを想いながら、
今日も暗い部屋で独りピアノを弾く。